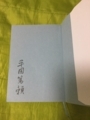アーシュラ・K. ル=グウィン 著
脇明子 訳
(サンリオSF文庫 1979年刊行)
1978年から1987年のあいだ存在していたが、いまはもうない『サンリオSF文庫』の一冊。貴重な品を貸して頂いた。
普通ならサンリオというとキティちゃんとかなんだろうけど、私にとっては中高生時代愛読した『詩とメルヘン』の出版元。なので出版社があるとは認識していたが、田舎育ちの悲しさ、SF文庫の存在は結構最近まで知らなかった。
職業病で、本編を読むより前に、巻末にある同文庫のラインナップを覗いてしまう。ル=グウィンの他にも、フィリップ・K・ディク、ウィリアム・バロウズ、レイ・ブラットベリと、ウキウキしてくるような人選。読みたい作品も多い。でも残念ながら、この文庫シリーズは、もはや存在しない。
ル=グウィンは、『ゲド戦記』の作者として、日本では特にジブリアニメを通しておなじみ。他にも『闇の左手』『所有せざる人々』(どちらもハヤカワ文庫SF)などたくさんの代表作があるが、個人的には、絵本『空飛び猫』(講談社文庫)の作者という方が馴染みが深い。
宮崎駿氏は、80年代から『ゲド戦記』シリーズを作品化したくて交渉してたそうだけど、ル=グウィンときたら日本のアニメすら観たことがなく、最初は断ったのだとか。数年後に『となりのトトロ』を観る機会があり、映像化するならこの監督に撮ってもらいたい考えを変えた。紆余曲折の末、監督が息子の吾朗氏に移ってしまったのは、ご存じの通り。
トトロの世界を評価する考え方は、ル=グウィンの生い立ちを考えるとなんとなく理解できる。父は著名な文化人類学者。母は、その父が深く関わったインディオ「イシ」という男性の評伝を書いた人物。
そのあたりは、池澤夏樹編集の河出書房版『世界文学全集 近現代作家集Ⅲ』にも載っていた鶴見俊輔の評伝「イシが教えてくれたこと」に詳しい。思想家として著名な鶴見氏なので、難しいのかなと思っていたが、文章が平易で驚くほどわかりやすい。とてもおもしろかったので、ル=グウィンに興味を持つ方ならぜひ。
この作品は、そのル=グウィンよる長編SF小説。突飛とも言える発想が、明快な文章と深い洞察に支えられている。
ある日、夢をみると、その夢が本当になり、現実を書き換えてしまう能力を与えられてしまったオアという青年が主人公。夢をみないように、睡眠薬に頼り続け、ついに薬を不法に取得したかどで、「強制治療」に送りこまれてしまう。
ヘイパーという博士に、暗示をかけてもらうことで、夢を制御しようとするのだけど…。
現実を変えてはいけないと考えるオアは、みる夢の効果をなくすことを望むが、ヘイパー博士は、夢の効力を使って、世界を「優生学的に優れたよりよい世界」にしようと考え、オアを利用し続ける。そのたび世界は、めまぐるしく変わり続け、オアの潜在意識や無意識の抵抗が、世界を混乱に陥れる。
人間の力で、自然や社会をねじ伏せようとするヘイパー博士の野心は、ある種欧米的。東洋人の端くれである自分は、本能的に、あるものはあるがままにしておく方がいいと感じるオアの姿勢の方に、どうしても共感してしまう。
あとがきによると、「天のろくろ」という作品タイトルは、『荘子』英語版の「誤訳」からつけられたのだそう。たとえ誤訳だったとしても、訳者も言っている通り、このタイトルから紡がれる世界だからこそ味わい深い。
どんなに世界をよくするためであっても、人工的に手を加えれば、変えるつもりのなかったどこか見えない部分も変わってしまい、世界はどんどんいびつになる。
この本が訳され、出版されてもう35年がたったことになるが、当時より今の時代の私たちの方が、このことを痛感できるのでは?
もしどうしてもいじらないといけないなら、オアのような人物に制御してほしい。ヘイパー博士ではなく。でも実際は、そううまくいかない。
自分のふるさと福島が、東京電力営業の福島第一原発の事故で、散々踏みにじられたのを目の当たりにしたせいか、特に強くそう感じる。
そういったストーリーだけでなく、丁寧に編まれた細部もこの本の魅力のひとつ。久しぶりに読書のおもしろさに突き動かされ、ページをめくる指が止まらなくなった。